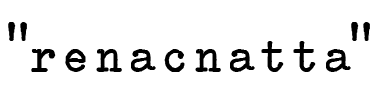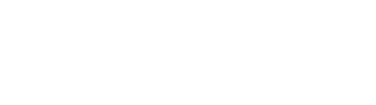人生に寄り添う、タイムレスな着物。丹後ちりめんが描く「雲」が導いたものづくり | renacnatta STORY

2016年のスタート以来、さまざまな伝統工芸とのコラボレーションを手掛けてきたrenacnatta(レナクナッタ)。これまでスカートやジュエリー、バッグなど現代のライフスタイルに寄り添うアイテムを多数展開してきました。
そして2024年8月、ブランド初となる着物のコレクションが誕生。


一生に一度の晴れ舞台を彩り、袖を切ることで年齢を重ねても長く愛用いただける「一生着られる振袖」。そして、職人の手仕事を知り、文化を纏う訪問着「連なる伝統が織りなす着物」のふたつをみなさまへお届けします。
振袖と訪問着は、同じデザイン。本コレクションの軸となる振袖を作るにあたり、“何歳になっても馴染むタイムレスなデザイン”を追求したことで、幅広い年齢の方に纏っていただける一枚が完成し、このような展開が可能になりました。
構想から誕生まで約3年の歳月を要した「Kimono Collection」は、レナクナッタ代表・大河内の「伝統工芸に貢献したい、伝統の真ん中で勝負してみたい」という思いから生まれたものです。丹後ちりめんに引き染め、挿し友禅、金彩、和裁と職人たちの技術のバトンにより一枚の美しい着物ができあがります。
そのスタートともいえる白生地を織り上げるのは、京都の田勇機業株式会社。創業1931年 、93年の歴史を持つ丹後ちりめんの織元です。

引き染めや挿し友禅、金彩の技が光るのも白生地の美しさがあってこそ。今回は、丹後ちりめんのなかでも、より美しい光沢感を持つ緞子(どんす)と呼ばれる生地を使用しました。
緞子は高級な反面、生産が難しく傷が生じやすい織物です。大きな雲を織り込んだデザインには、田勇機業の卓越した技術が活かされています。

「大河内さんが、生地の良さをとても上手に引き出してくださいました」。振袖の仕上がりに笑顔を見せてくれたのは、田勇機業株式会社代表取締役・田茂井 勇人さんです。
伺ったのは、細い生糸から一枚の白生地が生まれる田勇機業の工房。その現場を巡りながら、レナクナッタと丹後ちりめんとの出会い、今回の振袖が生まれるまでのストーリーをお伝えします。
理想の着物へと導いてくれた、「雲柄」の丹後ちりめん

「レナクナッタの着物には、田勇機業の丹後ちりめんを使おう」。コレクション計画当初から、大河内にはその思いがありました。
田勇機業とレナクナッタが出会ったのは、今から約4年前のこと。大河内が工房へ足を運んだことがきっかけです。
田勇機業の織物は、細い生糸を1本の糸に撚る(よる)ところからスタートします。丹後ちりめんの特徴である“シボ”と呼ばれる表面の凹凸は、よこ糸にかけた強い撚りからから生まれるものです。
たて糸は小さな糸巻から大きな糸巻へと巻き取られ、やがて織機でよこ糸と出合い、一枚の丹後ちりめんが完成します。
長年にわたり受け継がれてきた織物の技術、仕上がりの素晴らしさはもちろん、工房で目にした作業風景の美しさは大河内の心に強く残るものでした。

実はレナクナッタには、田勇機業の生地を使った洋服づくりにチャレンジした過去があります。
しかし、販売は完成間近で断念。「このアイテムではデザインの良さも、田勇機業の生地の良さも活かしきれない」。本当に納得がいくものをみなさまにお届けしたいという大河内にとって、それは苦渋の決断でした。

「あのときは良い意味で、大河内さんのものづくりへの思いの強さを実感しました。洋装の生地は和装に比べ幅が広く、製造できる織機が限られます。一方で、今回のような和装生地であれば、生地の種類や柄などさまざまな提案が可能です。雲柄をあしらった緞子(どんす)も、着物ならではの生地になります」
今回セレクトした「雲柄」は、かつての大河内が一目ぼれしたもの。まだ着物を作ろうという発想がなかったころ、田勇機業で目にしていた柄でした。織り方の技術によって、真っ白な地に雲の柄が浮かび上がる、そんな生地です。

着物の制作において、大河内はデザインの決定に行き詰まった時期があります。
今回のコレクションの軸となる、振袖のコンセプトは「一生着られる振袖」。袖を切ることで年齢を重ねても纏える着物を目指すなら、振袖としても訪問着としても美しく成立するデザインでなければいけません。
華やぎと静寂とが共存するデザインとは何なのか。約半年にわたりその答えを探し続け、たどり着いたのが、かつて田勇機業で目にした雲柄の存在でした。
まだ着物を作ろうという思いがなかったころに出会い一目ぼれしていた雲柄の丹後ちりめん。純白の一枚を空に見立て、時のうつろいを表現したグラデーションカラーに仕立てたら……。
そこへ手描き友禅で雲柄を足し、金彩で輝きを表現できたら理想の仕上がりになるのではないか。新たなアイデアが次々と大河内のなかで浮かび上がります。
雲柄との再会により、レナクナッタの着物づくりは再び完成へと走り出したのでした。
卓越した職人技によって初めて生まれる、絹織物の艶やかさ

レナクナッタがセレクトした雲柄の絹織物には、田勇機業の卓越した技術がふんだんに活かされています。
田勇機業が得意とするのは、撚糸(ねんし)と呼ばれる糸に撚りをかける技術。絹織物の一大産地である丹後地方でも、撚糸を手掛ける織元は決して多くありません。着物産業の衰退や人手不足が影響し、伝統の技を今に残す織元は年々減少しています。
「自分たちで撚った糸を自分たちで織るからこそ、仮にトラブルが生じてもすぐに対処できます。撚りムラのある糸は使わないなど、その時々に応じたフォローが可能です」
海外から輸入される糸は、大量生産であるがゆえに撚りムラの可能性も大きくなります。一方で、生糸の巻取りから職人が手をかけ、ていねいに撚られる田勇機業の糸なら安心して織ることができる。その信頼感から、糸のみをオーダーされることもあるのだと田茂井さんは教えてくれます。

また、絹織物の美しさを生み出すのが田勇機業の織りの技術です。「丹後ちりめん」と呼ばれる織物は、シボのある生地だけではありません。たて糸の上げ下げで美しい柄を織りだす“ジャカード”も丹後ちりめんであり、田勇機業を代表する絹織物のひとつです。
「レナクナッタの着物には、このジャカード生地が使われています。なかでも緞子(どんす)と呼ばれる、たて糸を表面に出した上質なものです。たて糸をより多く見せることで、緞子ならではの光沢感が生まれます」
緞子は、たて糸の上げ下げが難しく生産に高い技術を要する絹織物。織る際に糸同士が絡み合うリスクが高く、平織の生地に比べ完成には倍の時間を要するといいます。

また、緞子の艶やかさは、わずかな傷さえも浮かび上がらせてしまいます。今回のデザインは大きな雲柄。フラットな面が広いぶん、ごまかしもききません。
「織るのは簡単ではありませんでした」そう苦笑いしながら、田茂井さんは続けます。
「今回のような緞子は、今では仕立てる織元も少ない貴重なものです。さらに、手染めに挿し友禅、金彩と職人の手が加わっている。インクジェットによる染めが主流となる現代だからこそ、より価値ある着物になったと感じています」
艶やかな絹織物を織るところから始まる、レナクナッタの着物づくり。田勇機業で織られた反物は、工程ごとに職人たちの手を渡っていきます。そして今回ようやく、その完成形を田茂井さんに目にしてもらうことができました。
「色の組み合わせも美しく、生地の良さ、柄の良さを本当に上手に引き出してもらえたと思います」
丹後ちりめんとの出会いのきっかけにもなった田勇機業の絹織物。初めての出会いから数年を経て実現したコラボレーションアイテムは、伝統工芸の技術を最大限に活かした「着物」というかたちで、みなさまへとお届けします。
着物を通して、伝統工芸の「普遍的な価値」を未来へ

レナクナッタがコラボレーションする伝統工芸の多くは、需要減退や後継者不足などの問題を抱えています。また、分業制の産業も多く、どこかひとつが欠ければ成り立たなくなってしまうのが現状です。
伝統産業の枠ともいえる着物産業も、まるで業界全体が運命共同体のようだと表したうえで、田茂井さんは続けます。
「作るところから売るところまで、どの工程が欠けても着物産業は成り立ちません」
そんな危機感とともに、ものづくりのプロフェッショナルたちが手を携え、作り上げる分業の魅力も教えてくれました。
「仮に白生地に傷ができたとしても、職人の技術があれば染めたり柄を置いたり、仕立ての工夫などでカバーしてもらえます。傷を傷として終わらせなければ、生産コストを抑えることもできるかもしれません。今回のような難しい生地にも挑戦できるなど、それぞれがお互いをフォローし合うことで、本当に良いものづくりが実現すると思っています」

各領域の職人が、細やかな連携をとりつつ力を発揮することで実現する伝統工芸の世界。そこには、はるか昔から受け継がれてきた職人たちの技術と思いがあります。
私たちは、伝統工芸の世界に深く関わる中で、現代の感性やライフスタイルに調和する新しいものづくりの提案を続けてきました。それは単なるアイテムの提供にとどまらず、世代を超えて愛され続けるものづくりを通して、普遍的な価値を表現することでもあります。
今回誕生したタイムレスな着物は、まさにその哲学を体現したものです。一枚一枚に、日本の伝統工芸が織り成す手仕事の美しさが込められています。
着物を纏うことで日本の文化に触れていただけたら。そして、長く愛され続ける「もの」の素晴らしさを感じていただけたなら、そんなに嬉しいことはありません。
執筆:永田 志帆
撮影:小黒 恵太朗(インタビュー撮影)、渋谷美鈴(商品撮影)
編集:吉田 恵理