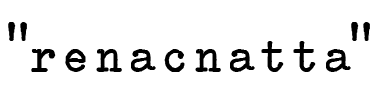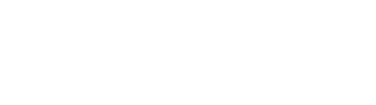京都の伝統工芸「金彩」を纏うイヤアクセサリー 「Kinsai Collection」
renacnatta(レナクナッタ)の「Kinsai Collection」は、京都の伝統工芸である金彩を、イタリアのシルクに施したイヤアクセサリーコレクションです。
京都で活動する金彩作家の上田奈津子さんとコラボレーションし、金彩をイヤアクセサリーというおしゃれで気軽に身に付けられるアイテムへと落とし込んでいます。
「Kinsai Collection」に込められているのは「ひとりでも多くの人に金彩の美しさを知ってもらい、楽しんでもらいたい」という思い。
その背景には、金彩の価値をもっと広めていきたい、美しい技術であるにもかかわらず衰退の一途をたどっている現状をなんとかしたいという思いがあります。
今回は、「Kinsai Collection」のラインナップや魅力、作家である上田さんの思いをご紹介します。
「Kinsai Collection」で京都の伝統工芸を身近に

京都の伝統工芸金彩を、イヤアクセサリーという気軽に身に付けられるアイテムに落とし込んだ「Kinsai Collection」。
京都で金彩職人・金彩作家として活動する上田さんとのコラボレーションは、「金彩が着物だけに使われているのがもったいない」という思いからスタートしました。
もともと金彩は、振袖や留袖といった高級な着物に施されるもの。ですが、アクセサリーという小さなアイテムであれば、もっと気軽に、もっと身近にその美しさを纏うことができます。
また金彩は染め上げた絹の生地に施す伝統工芸であるため、レナクナッタ代表の大河内が暮らしていたイタリアのシルクとも相性のいい技術です。金彩とイタリアのデッドストックシルクを組み合わせれば、今までにないジュエリーが生まれるのではと私たちは考えました。

そんな「Kinsai Collection」で展開するのは、白地や黒地の小さな半球体に金彩を施しジュエリーのように見立てたものや、イタリアンシルクの柄に合わせて金彩を施したアイテム。金彩はすべて、上田さんが1点1点、手描きで施しています。
「Nero」「Bianco」などのシリーズは、無地のイタリアシルクにフリーハンドで筒描きを施しています。本来、金彩は着物の模様に合わせて描くものですが、それに囚われすぎない自由な発想で金彩の魅力を引き出します。

また、ピンクと紫の色合いが美しいイタリアシルクに金彩を施した「Rosa」「Viola」は、淡い水彩画のような生地に、手書きならではのポップな柄がよく映えます。こちらの金彩は、ゴールドとシルバーの2種類があり、それぞれ違った美しさを楽しめるデザインです。

糊で描かれる、小さく繊細な模様たち。控えめかつ上品な輝きを生み出すため、箔はキラキラと光るものから落ち着いたマットな輝きのものまで、デザインに合わせてセレクトしています。
糊の上にていねいに箔を貼り付ければ世界でたったひとつ、ぷっくりとした立体感が魅力の「Kinsai Collection」の完成です。
また、購入頂いたアイテムの金彩が剥がれてしまったりくすんでしまったりした時はリペアも対応しています。レナクナッタ公式HPよりお問い合わせいただけます。
金彩とは?京友禅に華やかさを添える伝統技術

このアイテムの主役である金彩は、安土桃山時代から江戸初期にかけて確立したといわれる伝統工芸の技術で、主に京友禅の着物などに施され、華やかさを添えてきました。別名「きんだみ」とも呼ばれ、染めた絹の生地に金や銀の箔、金粉などを接着加工しています。

着物に施された金彩
また、ひとくちに金彩といっても、その加工技術はさまざま。筒描き、押箔、摺箔、砂子技法などが目的に応じて使い分けられます。
その中で「Kinsai Collection」で用いられるのは筒描きと呼ばれる技法です。筒描きは、筒から出る糊で線を描き、糊が乾いたのちに金箔をかぶせます。金箔を剥がすと糊の部分にのみ金が付くため、細かな模様を施すことが可能です。
金彩の技術はどれも高い技術力を要するもので、その習得には長い年月が必要です。
ですが、着物離れの影響で先染め織物、西陣織の需要が減り、それと共にどんどん衰退しています。約50年ほど前、年間1650万反ほどあった京友禅の生産量も、現在は30万反〜40万反まで減少したといわれています。
同時に数が減りつつあるのが、金彩を施す職人たちです。職人が減るということは、使用される金箔の量も減り、金箔を卸す業者も減少するということ。こういった悪循環によって伝統工芸は、衰退の一途を辿っています。
なかには、後継者が見つからないという高齢の職人や、技術に見合う賃金が得られず、自分の代でやめるという職人も存在するといいます。
金彩を私たちの世代で終わらせない

そんな状況の中、私たちレナクナッタがタッグを組んだのは京都で金彩職人・金彩作家として活動する上田さん。
現代まで当たり前とされてきた職人の働き方を変えたいという意思のもと、金彩の雇われ職人であった母とともに老舗がひしめく京都で「金彩上田」を立ち上げています。
上田さんは、最初から金彩職人として活動していたわけではなく、以前はタータンチェックの専門店で働いていました。
スコットランドで生まれたタータンは、氏族や一族を象徴する、家紋のような役割を果たします。それぞれの柄や名前の意味を知るうちに、日本の伝統や自分のアイデンティティを感じられるものに興味を持ったそう。
その背景にあったのが、生まれた時から雇われの金彩職人だった母の存在です。家紋が入った着物や伝統的な柄たちは、上田さんにとって子どものころから身近な存在でした。
やがて、上田さんは特殊技術にも関わらず、見合った賃金をもらえていない職人の環境に疑問を持ちはじめます。
「雇われてやるよりも、自分たちでやらない?」
そう母に声をかけたのは、自身が退職を考えたタイミング。上田さんは母の弟子として、2人で金彩上田を立ち上げます。当初、雇われの金彩職人だった母は独立を渋ったそう。それでも上田さんには、適正な価格設定のもとで仕事をしたいし、そうあるべきだという考えがありました。
上田さんが個人の目標として掲げているのは「技術に見合った収入を得て、職人や作家も当たり前の生活を送る」こと。そのためには、いつか自分のブランドを持たなければと語ります。
「ブランドを持つのは、自分の夢というより、やらなきゃいけない使命のような感じです。それをやらないと、次の世代には繋がらないから。金彩を私たちの代で終わらせるのは本当にもったいない」 金彩上田では技術を売る仕事として、和柄にとらわれない着物の直しやオーダーメイドを手がけています。ときには、箔を使わないふんわりした絵柄や、エコバックなどの制作も。
上田さんは「美しく輝く金彩を絶やすことは、日本のファッション文化の損失」「ひとりでも多くの人に金彩の美しさ、楽しさを知ってもらいたい」という思いを胸に、レナクナッタの「Kinsai Collection」をはじめ、多方面で活躍の幅を広げています。
上田さんとのコラボレーションである「Kinsai Collection」は、いまやレナクナッタを象徴するアイテムのひとつです。彼女との間では、いつか金彩で埋め尽くされたドレスを作りたいという願望も生まれています。
イヤアクセサリーをきっかけに、金彩という素晴らしい技術を世に広めるお手伝いができる。私たちはそのことをとても嬉しく、そして楽しく感じています。
和にとらわれない美しさ「Kinsai」

上田さんのフリーハンドで美しい金彩が施される、「Kinsai Collection」。SNSなどで「かわいい」、「きれい」と言われるアクセサリーたちは、「和」の世界にとらわれない魅力にあふれています。
上田さん自身も「和にとらわれてはいけない」と常に意識しているそう。元々フリーハンドの金彩は手がけていたものの、「Kinsai Collection」を通し、フリーハンドで描くことが自身の強みとあらためて感じたといいます。
「今まで金彩に触れる機会が少なかった方の反応を見られるのはすごくありがたいし、新鮮でうれしい」
イタリアのシルクに描かれる上田さんの金彩は、「金彩は着物に施される技術」という概念を抜け出したもの。ジャンルにとらわれることのない「Kinsai」としての輝きを放っています。
その輝きは、過去から現代へと姿を変え、未来へと続く伝統工芸の美しさといえるのかもしれません。
「金彩は、表現方法次第では金属のようにも、刺繍のようにも、宝石のようにも見せることができる、自由度の高い楽しい加工技術です」
フリーハンドで絵画のような金彩加工を生み出す上田さんは語ります。金彩は、祝い着や晴れ着などに欠かせない、日本の伝統的な装飾加工。その上品な華やかさや煌びやかさを纏えば、すこし特別な日になるかもしれません。
「私の仕事は、キラキラピカピカで誰かの気持ちをアゲること」
唯一無二の輝きを放つレナクナッタの「Kinsai Collection」には、そんな上田さんの仕事への思いが込められています。
また、金彩は箔の種類や技法、天気、場所によって輝き方が違って見えることも魅力のひとつです。
その日、その場所で、耳元を異なる表情で彩るイヤアクセサリーたち。「Kinsai Collection」を直接手に取り、その美しさを体感していただければと思います。