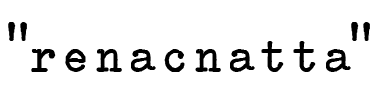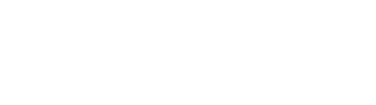伝統の帯を超え、現代を生きる日常へ。「白練」と「墨黒」が織りなす、西陣織の未来図 | renacnatta STORY

renacnatta(レナクナッタ)の「Nishijin-ori Collection」に、新たなアイテムが加わります。
2020年のウエディングドレスから始まり、四季のスカート、そしてコロナ禍で多くのメディアに取り上げられたマスクまで。これまで西陣織リニスタグループとのコラボレーションで生まれてきたアイテムたちは、いずれも「文化を纏う」というレナクナッタのコンセプトを体現し、多くの方に愛され続けてきました。
そして2025年10月、約4年ぶりとなる新作が登場します。今回のアイテムは、これまでのボリュームのあるAラインスカートとは趣を異にする、シャープで洗練されたシルエットが印象的な西陣織スカート。

白練(しろねり)と墨黒(すみくろ)の2色で展開されるこのスカートには、レナクナッタ代表・大河内と西陣織リニスタグループ代表のサカイタカヒロさんがタッグを組み、新たに立ち上げたスキンケアブランドSericyへの思いも込められています。

伝統的な帯作りの枠を超えて現代のライフスタイルに寄り添うアイテムを展開する背景には、どのような業界への思いと未来への展望があるのでしょうか。
西陣織の奥深い技術的な魅力から、業界が抱える課題、そしてレナクナッタとの長きにわたるパートナーシップを通じて見えてきた伝統工芸の新しい可能性まで、ふたりの見据える世界を紐解いていきます。
同じ糸から異なる表情を紡ぎ出す、西陣織の精緻な技

「西陣織って、よく刺繍と間違われるんですよ」
サカイさんのこの言葉に、西陣織の最大の特徴が凝縮されています。それほどまでに立体感があり、一見すると織物とは思えないほど豊かな表情を持つ。それが西陣織の真骨頂です。
西陣織は、京都の伝統工芸品として認定された織物で「先に染めた糸を使って織り上げる紋織物」というのが基本的な定義です。特徴的な柄の指定もなく、素材の縛りもない。一見すると特徴の少ない織物に思えます。
では、西陣織を西陣織たらしめるものは何なのか。それは「組織作り」という、非常に精緻な技術にあります。
「“組織”とは、布を細かなドット状に見立てた時の縦糸と横糸の交差パターンの設計図のようなものです。縦糸と横糸の絡ませ方によって、でこぼこ感や立体感を表現していきます。どの糸をどのようにして上に出すか、精密にコントロールすることで色の濃淡や立体感を自在に操ることができるんです」
そう言いながらサカイさんが見せてくれたのは、青い花や松、金銀の竹が美しく配された帯でした。

「たとえば、青い花と松の小枝の部分。異なる青に見えますが、実は同じ青糸を使用しています。青い花の部分は横糸の青がしっかりと表面に現れ、茎の部分は横糸の青と金が混ざり合うことで、同じ青でも明るい青を表現している。決して異なる色の糸を使っているわけではなく、組織の工夫だけでこの色の違いを生み出しているんです」

さらに、金と銀の竹の表情を見ていくと、縦糸の金、横糸の金、白の3種の組み合わせでこの2種類の竹を表現しているのがわかります。金の竹は縦横の金が。銀の竹は縦糸の金と横糸の白によって構成されているのです。

「完成するとただの一枚の布なのですが、組織の作り方、縦糸と横糸の絡ませ方によって、色の差やでこぼこ感を表現できている。『よくこんなことやってるな』と、見るたびに思います」
さらに、西陣織では太い糸も織り込むことができるため、より立体感のある表現が可能になります。組織作りの緻密さと、太い糸を使えるという特徴、この両方があって他の織物産地にはない立体感を実現しているのです。
そしてこの組織作りこそが、西陣織の職人技術の根幹であり、500年以上にわたって受け継がれてきた叡智の結晶でもあります。同じ色の糸を使いながら、技術と工夫で豊かな表現を生み出す。その精緻さと創意工夫に、西陣織の真価が表れています。
お互いの言葉の温度が合うからこそ、生まれるアイテム

サカイさんと大河内との出会いは、大河内がネクタイ用の広幅生地を探していたことから始まります。
「元々SNSで存在を知っていましたが、実際にお会いしたのはネクタイ用生地の相談で工房にいらした時が初めて。世代も近いですし、やり取りする中で感覚や価値観が近しいものを感じていました」
この出会いから誕生したのが、レナクナッタの中でも特に反響が大きかったアイテムのひとつ「一生着られるウエディングドレス」でした。最初はネクタイを作る予定だったところが、工房で出会った生地の魅力に大河内が圧倒され、ウエディングドレスというアイデアに繋がっていったのです。

その後も、四季をテーマにした4色展開のスカートや、コロナ禍で大きな話題を呼んだ西陣織マスクなどが生み出されていきました。いずれもレナクナッタを代表するアイテムとなり、多くのお客様から支持されています。

四季のスカートのうち、春を表現した「Nishijin Skirt - Primavera」
サカイさんがレナクナッタとのコラボで特に価値を感じているのは、コミュニケーションの質の高さです。サカイさんは、職人としての父の言葉や感覚を、お客さんに分かる形で伝える“翻訳”の役割。大河内とのものづくりでは、翻訳した言葉が驚くほどスムーズに伝わると感じているそうです。
「使っている言葉の温度感が近いんです。『こう言えば伝わるだろう』と思うことが、すんなり伝わる。それがある人じゃないと、一緒にものづくりはできないと思います」
大河内もまた、サカイさんとのやりとりに近しいものを感じています。特に西陣織マスクは、顔まわりにつけるものということで色にこだわったアイテムでした。しかし、西陣織は糸を見ても、組織の作り方で色が全く変わるもの。
出来上がりをイメージして「こういう色がいいです」と色見本を見せると、サカイさんがピタリと合わせてくれる。その感覚は、サカイさんとだからこそ叶うものづくりなのかもしれません。

現在は西陣織の魅力を深く理解し、その可能性を広げる活動に取り組むサカイさん。もともと家業を継ぐつもりは全くありませんでした。
大学卒業後は大阪でバッテリー販売の営業職に就いたサカイさんですが、社会人3年目の頃、友人が副業を始めたのを見て「自分には何があるだろう」と考えた時、身近にあった西陣織に目を向けたのです。
「父の工場で出る端切れをもらって、ミシンでコースターを作ったのが始まりです。カフェの作家コーナーに置いたり、部活のような感覚でした」
そんな小さな試みから始まったサカイさんと西陣織の関係。しかし、ミシンで西陣織を扱ううちに、改めてその美しさに気づくことになります。
「現代の生活に西陣織は浸透していません。でも、ミシンで織物を縫う時に『なぜこんなに綺麗なのに使われず、なくなっていくと言われるんだろう。もったいないじゃないか』と感じました」
この思いが、サカイさんの人生を大きく変える出発点となりました。営業スキルを活かしてホテル向けのクッションなどを手掛けるようになりました。
「法人営業の経験があったから『こうやったら仕事になるんじゃないか』という感覚がありました。営業って、商材が変わっても売る人は売る。そのコツさえ分かっていれば大丈夫かなと」

西陣織を取り入れたホテルの一室。クッションやベッドスローが西陣織となっている
しかし、当時の工房では帯の規格である約36cmの幅でしか織ることができず、縦糸として使える糸は絹のみで、どうしても絹が入り、縮みのリスクや日焼け・摩擦に弱くなる。お客さんからの「広幅で織れればいいのに」「洗えるようにならないか」という声を父親と共有する中で、技術革新の必要性を痛感します。
その後、広幅織機を導入しポリエステルでも織れるようになったことで、サカイさんは会社を辞めて本格的に西陣織の世界に戻る決心を固めます。ただし、それは単なる家業継承とは一線を画すものでした。
「自分で新しい販路を開拓し、自分の売上を立てる形で戻りたかった。だから最初は帯の仕事もやっていませんでした」
元々、ゼロからイチを生み出すことが好きだったというサカイさん。大学時代はサークルを自分で立ち上げ、バンドでは作詞作曲を手掛ける。そんな創造への情熱が、伝統産業に新しい風を吹き込むことになったのです。
流行の主導権が変わった時代の現実と、未来のつくりかた

西陣織業界に本格的に戻って5年。サカイさんが日々肌で感じている業界の現状は、一般的に語られる“職人の高齢化”や“後継者不足”以上に複雑な問題を抱えています。
「職人の高齢化に輪をかけて、業界全体で新たな取り組みへの温度感が下がっていることが深刻です。年々需要が減っている中、新しい挑戦がますます難しくなっていく。さらに、流行の発信源が根本的に変わった今の世の中、業界も大きな流れが変わりつつあるように感じます」
雑誌やテレビが流行を牽引した時代には、川上側(メーカー)がトレンドを予想して商品を作り、それが市場で受け入れられるという循環がありました。しかし、SNSが影響力を持つ現代では、川下側(小売店など)から流行が生まれるという逆転現象が起きています。特に成人式という若い世代向けの市場では、この変化が顕著です。
「数年前までは『これを作っておけば大丈夫』というものがあった。でも今は『くすみカラーの振袖が流行』といった情報を正確に掴んで、商品を作らないといけません。みんな、何を作ったらいいかわからない状況になっています」

こうした現状を受けて、サカイさんは和装業界での大きな構造転換は、多くの関係者が存在するため容易ではないと冷静に判断しています。
「織元としてできることには限りがあります。だからこそ、違う仕事をして西陣織の認知を高めていく。和装業界じゃないところでもしっかりお金を作れるような仕事をして、結果的に西陣織業界を盛り上げていくというアプローチを試みています」
現在、サカイさんが手掛けるのは実に多彩なアイテムです。西陣織の生地をガラスと樹脂で挟んだお皿、御朱印帳、サコッシュなど。ECでの販売も展開し、特に御朱印帳は「軽い気持ちで作ったのにすごく売れて驚いた」と言います。

西陣織リニスタストアで販売している、御朱印帳と西陣織ガラス皿
「音楽も最初は安いギターから始めて、ハマったらこだわりますよね。西陣織にもそういう『入口商品』が必要だと思うんです。さまざまなアイテムに西陣織のエッセンスをしのばせて日常で触れてもらう機会を増やすことで、気づいたら西陣織との距離が近くなっている。時間はかかるかもしれませんが、自然に西陣織が馴染んでいく方法だと考えています」
西陣織の新しい可能性を探り続ける、ふたりの挑戦

今回のレナクナッタの新作について、サカイさんはこう語ります。
「継続したお仕事を続けていけることが、織元としていちばん大切なこと。今回で第5弾になりますが、このようなコラボレーションを重ねていけることが、心から嬉しいです」
今回の新作は、大河内とサカイさんが共同で立ち上げるスキンケアブランドSericyの制服としても位置づけられています。Sericyは、西陣織の精錬(せいれん)工程で出る副産物を活用したシルク由来のスキンケアブランド。“精錬”とは、絹についているタンパク質“セリシン”を取り除く工程のこと。この過程で得られるセリシンは天然の保湿成分として知られています。

スカートの色として選ばれた白練(しろねり)は、まさにこの精錬後の絹の色を表す伝統色であり、Sericyのブランドカラー。西陣織の製造工程そのものと深く結びついた色彩です。
また墨黒(すみくろ)は、西陣織の業界で古くから用いられる黒を表す言い方で、Sericyのブランド世界を引き締める二色目のカラーとして採用しています。
またこれまでのNishijin-ori CollectionのスカートがボリュームのあるAラインだったのに対し、今回は筒状の生地を折りたたむことでフィットさせる独特なシルエット。華美な装飾を削ぎ落としたデザインは、大河内が“Sericyの制服”として思い描いた、シンプルで誠実なブランドの姿を映し出しています。

生地に使用されるのは鳳凰の羽を抽象的に描いたデザインで、光がさすと織りの凹凸が浮かび上がりさまざまな表情を見せてくれる柄。鳳凰には、再生や循環を象徴する意味があり、レナクナッタとSericyに共通するものづくりの精神を表すものとして採用しました。
実はこの生地、以前サカイさんの工房で出会い、大河内が別のアイテムの生地として検討していたものでした。しかし、素材や製造上の制約から使えず、「いつか何かに使おう」と大河内の心の引き出しに大切にしまわれていた柄だったのです。2色の糸のみで色を表現するシンプルな生地は、サカイさんいわく「逃げ道がない難しさ」があるそう。
「振袖帯のように沢山の色で構成するのは、たとえるといろんな具材のおいしさを盛り込める鍋焼きうどんのようなもの。でも今回の生地は、素うどんを作るように、ごまかすことができないという難しさがあります。実力の見せどころです」
数年ぶりの「Nishijin-ori Collection」新作は、サカイさんと大河内の新しい挑戦Sericyを象徴するアイテムとして、西陣織の組織作りの技術がよりいっそう際立つものとなりそうです。このスカートを纏い、西陣織の美しさやそのエッセンスを日常で感じていただけたら、こんなに嬉しいことはありません。
執筆・編集:吉田 恵理
撮影:小黒 恵太朗(取材)、岡本依里(商品)
関連記事