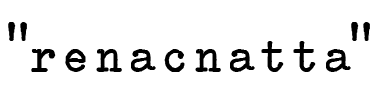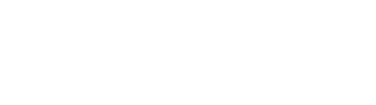日本と西洋、異なる文化の融合は「足し算」か「掛け算」か? │ るりこ×大河内 愛加 対談

renacnatta(レナクナッタ)代表、大河内 愛加が伝統工芸・伝統文化を未来へ繋げる方々と対談を繰り広げる本企画。今回のテーマは「日本と西洋の文化を組み合わせるときに意識することは?」。
「文化を纏う」をコンセプトに、イタリアと日本の素材や技術を組み合わせたアイテムを展開するレナクナッタ。その根底には、異なる文化を深く理解し、尊重した上で新しい価値を生み出す姿勢があります。しかし、伝統の核を守りながら現代に即した表現を模索することは、多くの挑戦を伴います。
そこで今回の対談のお相手として迎えたのは、日本舞踊家として活動しながらも、バレエやパントマイム、プロジェクションマッピングなど西洋の表現手法とのコラボレーションを精力的に行うるりこ(扇寿紡之華)さん。日本舞踊扇寿流師範としての顔を持ちつつ、着付けや茶道の知識も兼ね備え、来年からはパリを拠点に活動を広げる予定という、まさに日本と西洋の文化の架け橋となる存在です。
ふたりの共通点は「日本文化と西洋文化」どちらも知った上での表現活動やアイテム制作。それぞれの文化をどのように大切にし、現代に合わせた形で発信していくべきか。伝統を「囲って守る」のではなく「広げて守る」ためにやるべきことは何なのか。
同じように「日本と西洋」のふたつの文化を紡ぐふたりの対話から、伝統文化を未来へつなぐヒントを探ります。

るりこ(扇寿紡之華)さん
日本舞踊扇寿流師範、俳優、着付師。るるる企画主宰。日本舞踊や俳優業を中心に、国内のみならず海外公演にも多数出演。日本伝統芸能にまつわるバックグラウンドを軸に、異なる文化とのコラボレーションや企画を行う。内閣府×KADOKAWA クールジャパンコンテスト2020奨励賞受賞。第81回全国舞踊コンクール入選。(@ruricollage)
文化の本質を見極め、深く理解することから始まる

大河内:レナクナッタは、イタリアと日本の素材や技術を組み合わせたアイテム展開をしていますが、るりこさんも日本舞踊を軸に、バレエやプロジェクションマッピングなど異なるジャンルとのコラボレーションを積極的にされていますね。「日本と西洋の文化」の両方を採り入れた活動という共通点が私たちにはあると思っています。
るりこさん(以下敬称略):そうですね。私たちの出会いはSNSがきっかけでしたが、お互いの活動に共感して自然と繋がったような気がします。
大河内:るりこさんの大阪での舞台を観に行かせてもらったときは、日本舞踊の演目だけでなく、パントマイムやマジックショーなども組み合わさっていて、とても印象的でした。日本舞踊家でありながら企画もされる、そんな稀有な活動をされているるりこさんだからこそ、「日本と西洋の文化を組み合わせるときに意識すること」をお話してみたいと思ったんです。

大河内:それぞれの文化を融合させるとき、理解を深めていないと表面的なミックスとなって失敗してしまうこともあるかと思います。るりこさんは異なる文化を組み合わせるときに意識していることはありますか?
るりこ:たとえば、あいかさんが見てくださった舞台では、パントマイムやマジックの方とコラボしたのですが、素直に「これとこれは、コラボできますか」と伺いながら、専門的な部分はプロフェッショナルに任せることを意識して進めました。
大河内:それは大切ですね。私も、西陣織や金彩などの伝統技術と組み合わせる際、職人さんの専門性を尊重しています。
るりこ:逆に、先方がプロデュースして日本舞踊の要素を採り入れる場合は、先方に丁寧に説明することを心がけています。また相手の文化や背景を理解するために、作品を見たり実際に体験ワークショップに参加したりすることも大切にしています。
大河内:自分自身がその文化の中に入るというアプローチも、同じかもしれません。イタリアには15年ほど住んでいたので自然とその文化は身につきましたが、日本文化は京都に移住してから意識的に学んできました。職人さんのワークショップに参加したり体験させてもらったりして理解を深めています。
るりこ:見るだけでは、表面的な理解にとどまってしまいますよね。私は体験の中で発見するものこそが、一過性ではない長く続くプロジェクトを生み出す土台になると信じていて。実際、私がプロデュースしたジャグリングと和太鼓のコラボなど、今でも新しい作品を作り続けているものもあります。

るるる企画第三回本公演(撮影:宮井宗太郎)
大河内:私が拝見したるりこさんの舞台は、歌舞伎からパントマイムやジャグリングまで多彩な要素があるのに、不思議と調和が取れていました。そういった調和を生み出すために気をつけていることはありますか?
るりこ:舞台に限って言うなら「観る方にとって何が心地よいか」を考えています。特に伝統芸能は現代の生活リズムと乖離があります。日本舞踊は本来ゆっくりとした時間の流れで鑑賞されるものですが、YouTubeも1.5倍速で見たりするような現代では、90分同じテンポで見続けるのは難しい。

るりこ:だから、現代の時間軸に歩み寄る工夫として、テンポを上げたり、映える部分を凝縮してかいつまんで見せたり…ということをしています。
大河内:たしかに現代人の集中力は昔と違いますね。私たちも伝統工芸を現代のライフスタイルに合わせて表現することを考えているので、その部分に苦心する気持ちはよくわかります。
その中で私が大切にしているのは、その文化や技術の「核」となる部分の見極めです。文化の本質、核となる価値は何かを見極め、そこは守りながら変化させるべき部分を見定める。自身の体験や、職人さんとの対話を通して「この産業や職人さんが大事にしている、尊重すべきところ」を探る感じです。
るりこ:おっしゃる通りですね。扇子の使い方や、着物の畳み方ひとつとっても、日本舞踊の伝統としてのルールがあります。そこは守りながらも現代に寄り添う、バランス感覚ですね。
「足し算」と「掛け算」で考える文化の融合

大河内:文化の融合方法として「足し算」と「掛け算」という考え方ができると思っていて。「足し算」は日本と西洋の要素が両方見える形、「掛け算」は交わりで全く新しいものが生まれる状態です。るりこさんはご自身の活動をこの考え方に当てはめるとしたら、どちらが多いですか?
るりこ:私の活動は、表面的には「足し算」に見えるかもしれませんが、根本的には「掛け算」を目指しています。一般の方には足し算的な表現の方が理解されやすいのですが、本質的には両者が交わることで新しい価値が生まれることを意識しています。
たとえば日本舞踊×プロジェクションマッピング、はまさに伝統芸能と最新技術の「足し算」に見えるかもしれませんが、プロジェクションマッピングの映像は舞台でいうところの「大道具」や「美術」ような役目を果たしています。そういった意味で、根本的には足し算ではなく「舞台」という枠組みの中で「掛け算」をして、新しい見せ方や作品を生み出していると思っています。
大河内:私も全く同じ考えです。たとえばレナクナッタのリバーシブルスカートは、着物とイタリアシルクを組み合わせた「足し算」に見えますが、根底にはイタリア生活で身についた「自分の体に合った服を選ぶセンス」と、着物の「巻き付けて身体に沿わせる」文化の「掛け算」があるんです。

レナクナッタ「Dead Stock Collection」
るりこ:表面的な素材の組み合わせだけでなく、文化的背景や価値観の融合があるわけですね。あとは、お客様の知識や経験によっても変わってきますね。専門家相手なら「掛け算」の部分を強調できますが、一般の方には「足し算」として見せる方が伝わりやすい。お客様の層に合わせて表現方法を選ぶべきだと思っています。
大河内:るりこさんはヨーロッパでも公演されていますよね。そのときも日本と西洋の組み合わせをされているのですか?
るりこ:いえ、逆にヨーロッパではほとんど古典ばかりなんです。向こうではちゃんとした古典を見せられる人が少ないので、トラディショナルなものを見せてほしい、という要望が多いんですよ。
大河内:公演後の反応はいかがですか?
るりこ:特にフランスでは公演後にお客様との対話の時間が多いです。「あれはこういうストーリーだったんですか」と、歌詞がわからなくても推測して感想を言ってくださる方が多いんです。見方が違うなと感じますね。日本舞踊はわかりづらい部分が多いと思うんですが、ヨーロッパの方はそこをわからないで終わらせずに、自分の中で作品を解釈しようとする傾向があるように思います。
大河内:その違いは面白いですね。イタリアに住んでいた肌感覚としても、フランスは日本文化への理解や関心が早くから高かった印象です。
るりこ:そうですね。パリは京都とも姉妹都市で、歴史を守り継承してきた都市としての共通点があります。歴史的な価値を尊重する精神性が日本文化と通じるところがあって、それで親しみを抱いてくださる方が多いのかもしれません。
「囲って守る」から「広げて守る」へ

大河内:私たちもるりこさんとのコラボレーションを考えています。2025年10月に開催予定のレナクナッタツアーに、日本舞踊の鑑賞とワークショップを取り入れたいと思っているんです。伝統工芸に興味を持つお客様に、日本舞踊の世界にも触れていただく機会を作りたいのですが、どのような内容になるか紹介いただいても良いでしょうか。
るりこ:まず簡単なお座敷舞のようなものを見ていただければと思います。ワークショップは、歌を実際に歌ってみたり、踊りを教えたり。京都にまつわる言葉が入っている歌などは、意味はわかるけど現代ではあまり使わない美しい言葉に触れていただけるので面白いかもしれません。
大河内:あとは、日本舞踊の仕草の美しさを日常に溶け込ませるようなワークショップもできないかなと思います。たとえば、着物を着たときに見える綺麗な手の仕草とか。そういう動きを教わることも、違う文化を纏う形になるのではないかと。
るりこ:日本舞踊の歴史についても少し触れておくと理解が深まるかもしれません。実は日本舞踊の起源は、出雲の阿国が京都の河原町で始めた踊りにあります。当時は着物をはだけさせながら踊る、いわばストリップショーに近い要素もあったと言われています。その後、幕府の禁止などを経て歌舞伎が生まれ、その中から踊りの要素だけを抜き出して一般の習い事となったのが日本舞踊です。
大河内:知りませんでした。ストリップショーからはじまり、今は伝統芸能。歴史を知ると面白いですね。

るりこ:元々はそんなに高貴なものではなかったのですが、今は馴染みが少ないということもあり、格式高い印象になってしまいました。
大河内:伝統文化の世界は、「囲って守る」姿勢も強いですしね。
るりこ:まさに「囲って守る」と外側の人からはわかりにくいですし、今の時代には合わなくなってきていると感じています。これからは「広げて守る」という方向性が重要ではないでしょうか。
大河内:本当にそうですね。伝統工芸の世界も同じで、内側だけで守り続けるのではなく、より多くの人に開かれた形で伝えていくことが求められていると感じます。変化を恐れず、興味を持ってくれる方々に開かれた形で伝統を伝えていくことが、結果的にその文化を守ることになると思います。
るりこ:そして初心者の方に気軽に触れていただける入口を作ると同時に、より深く踏み込みたい方にも楽しんでいただけるよう、両方のアプローチが必要だと考えています。そうすることで、裾野を広げながらも伝統の深みを保つことができるのではないでしょうか。
大河内:入口と深み、両方を用意することで伝統を繋げていく…まさに理想の形ですね。
るりこ:もうひとつ大切にしたいのが、海外での評価が国内での再評価に繋がる「逆輸入」の流れです。今、ヨーロッパでは日本文化ブームがありますが、それが日本国内での関心喚起につながっていないのが残念なんです。
そのために私は来年からパリを拠点に活動しようと考えています。来年の5月頃から移住予定ですが、完全に日本を離れるわけではありません。ヨーロッパと日本を行き来しながら、文化の橋渡しをしていきたいと思っています。
大河内:海外での評価が国内での活動発展に結びつく好循環を作りたいですね。引き続き、一緒にいろいろとやっていきましょう。

関連記事